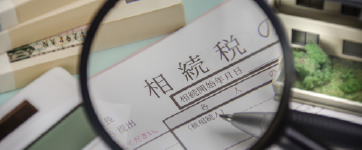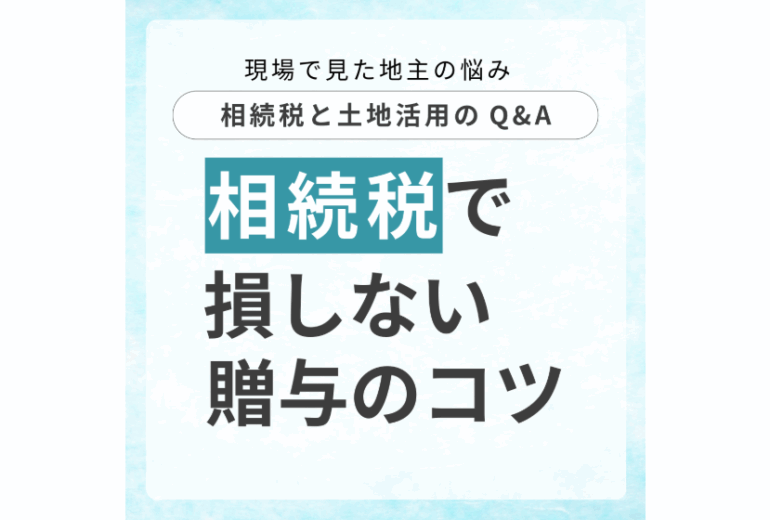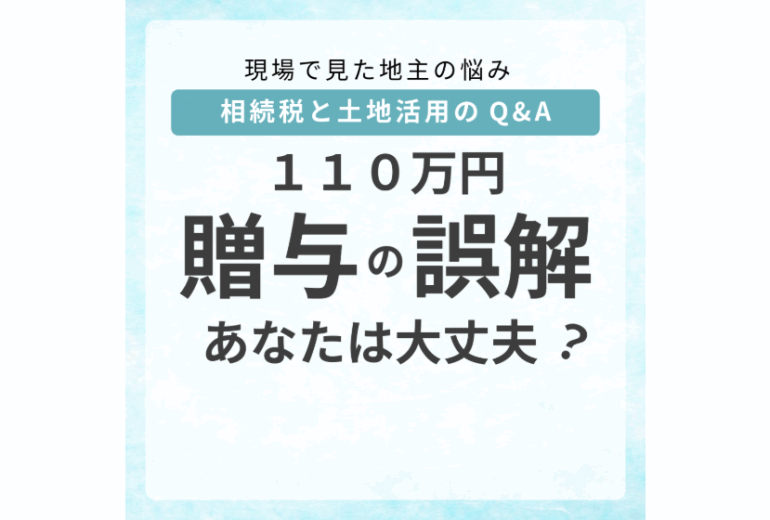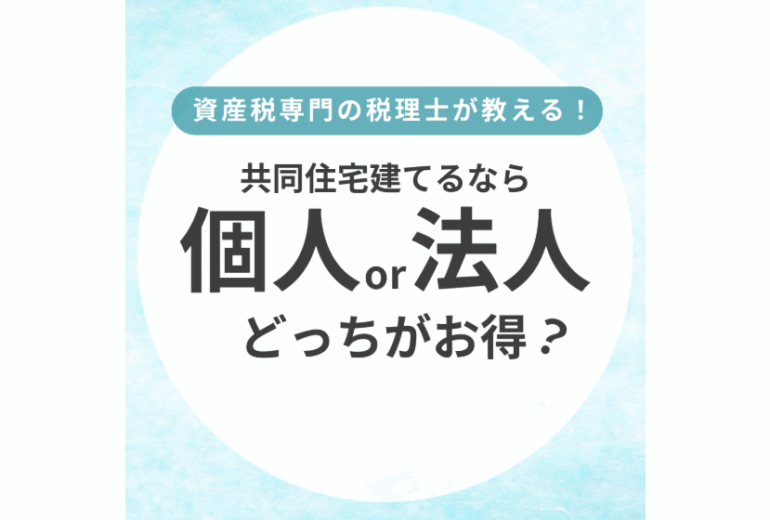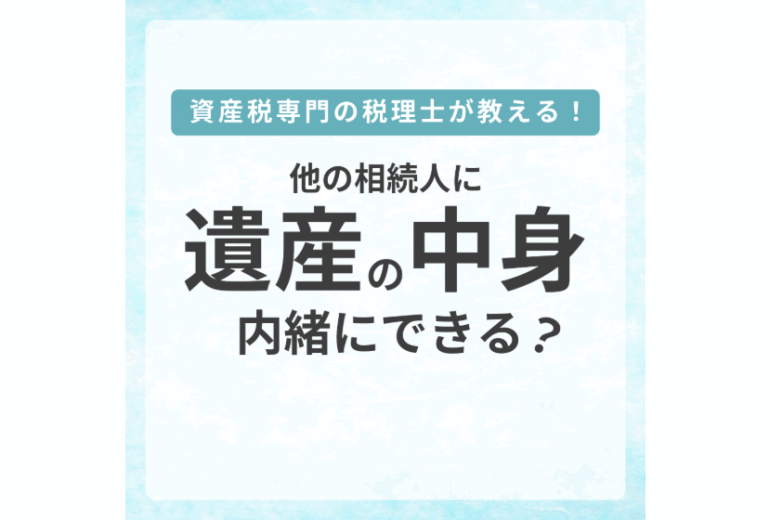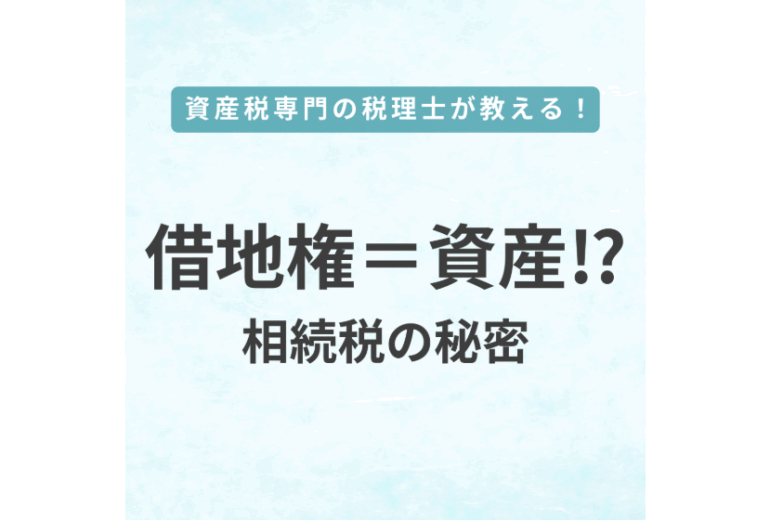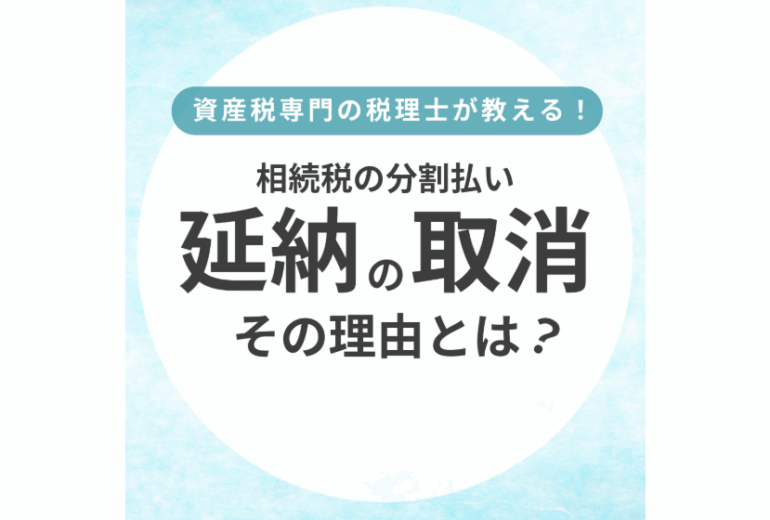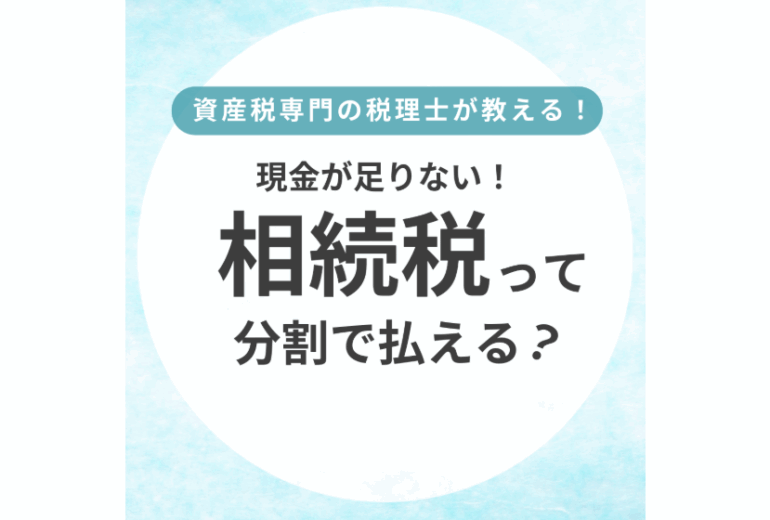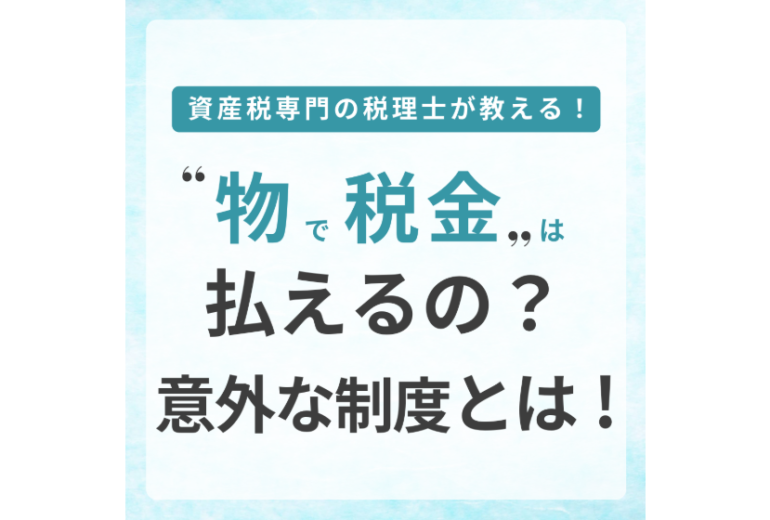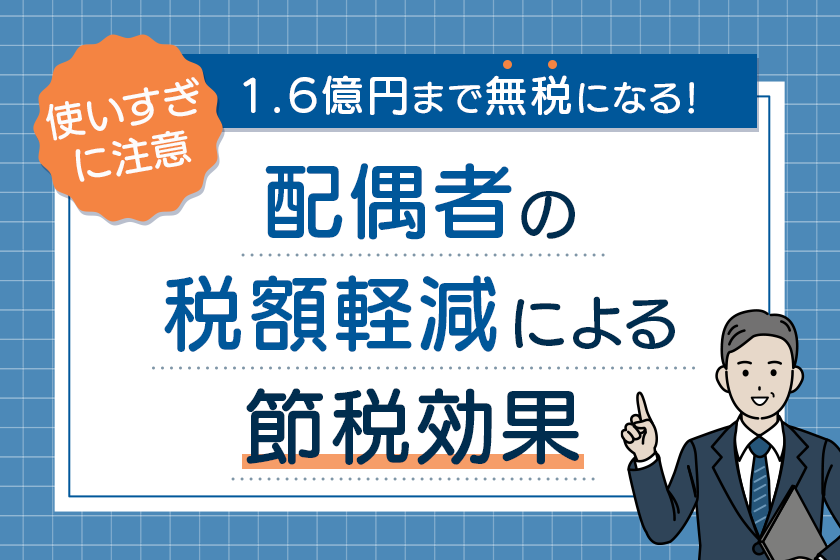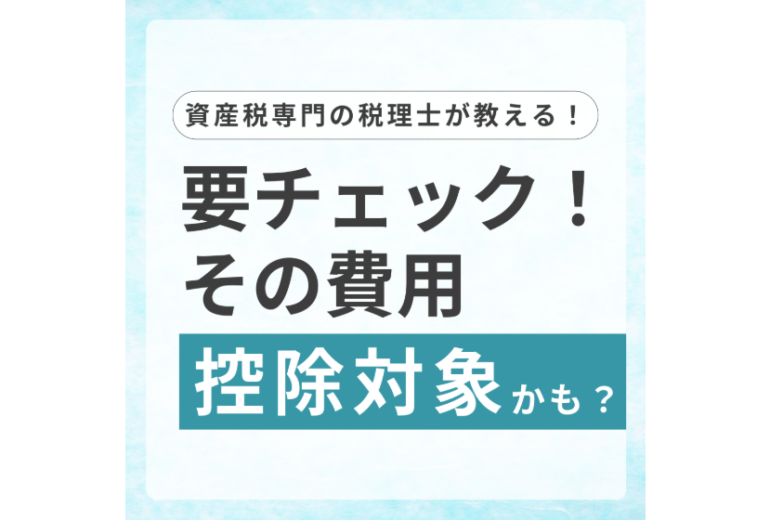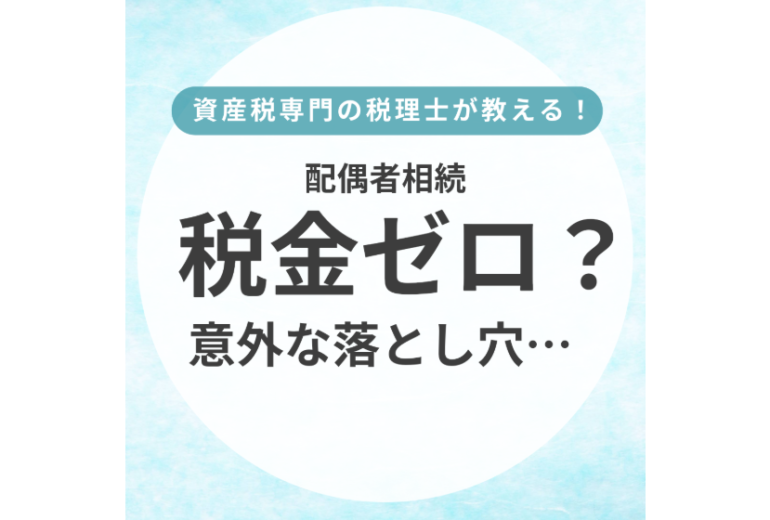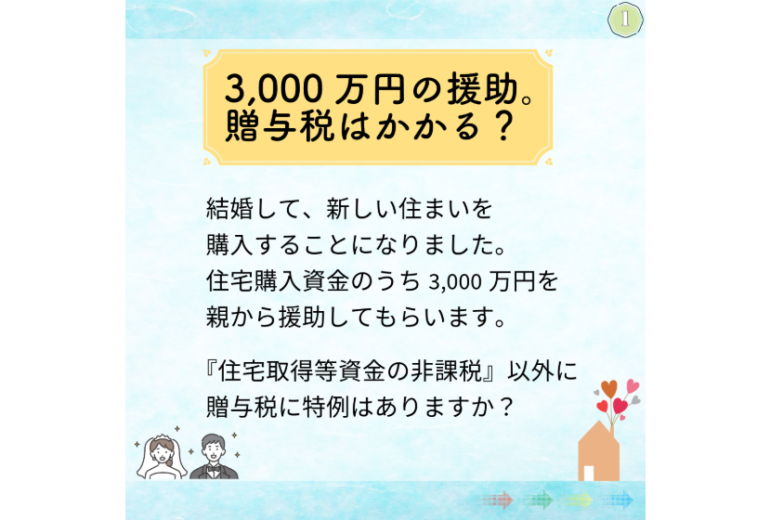相続税には支払う税金を少なくしてくれる各種制度が設けられています。
その中でも、「配偶者の税額軽減」は支払う税金に最も大きな影響があります。
しかし、この制度を使いすぎると結果的に税負担が増えることも…
この記事では、「配偶者の税額軽減」の仕組みや注意点についてご紹介します。
「配偶者の税額軽減」のしくみ
最低でも1億6,000万円までは無税
死亡した人の配偶者であれば、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額
もし、1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分までなら ⇒ ゼロ円
相続税の配偶者控除の適用要件
配偶者控除を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 相続時点で戸籍上の配偶者である
- 申告期限までに遺産分割が決まっている
- 相続税の申告書を提出している
1.相続時点で戸籍上の配偶者である
この軽減が適用できるのは相続時点で戸籍上の配偶者に限られます。
したがって、離婚した配偶者には軽減の適用はありません。
また、事実婚や内縁関係の当事者は、戸籍上の配偶者ではないので適用はありません。
2.申告期限までに遺産分割が決まっている
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整っている必要があります。
お得な軽減を適用するために、申告期限に間に合う段取りで話し合いを進めましょう。
3.相続税の申告書を提出している
この制度は自動的に適用されるものではありません。
必ず、相続税の申告書を税務署に提出しなけばなりません。
なお、相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
この制度を使いすぎると…
次の相続で税金が高額になるデメリット
できるだけ多くの財産を配偶者が取得すれば、相続税は小さくなることがわかりました。
でも、目先の税金を節約したいからといって、財産の多くを配偶者に寄せたとします。
そうすると、この後の相続で問題が生じます。
なぜなら、配偶者が引き継いだ財産に対しては、2回目の相続税がかかるからです。
例えば、死亡した人の全財産が1.6億円だったとします。
この財産全てを配偶者が取得すれば、子どもを含めた家族全体の相続税額はゼロ円にできます。
しかし、その配偶者が亡くなるとき、最初の相続よりも税金は高くなってしまうのです。
なぜ2次相続の方が税金が高くなるのか
2次相続では「相続人の数」が減ります。
例えば、子どもが2人いる家庭でお父さんが亡くなったとします。
最初の相続では「母・長男・長女」の3人が相続人でした。
次に、その数年後にお母さんが亡くなりました。
2次相続の相続人は「長男・長女」の2人が相続人です。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続人の数が1人分減ってしまうと、基礎控除額が減り、結果的に相続税は高額になるのです。
無駄な税金を払わないために
配偶者の方が使い切れないほどの金銭を相続させるのは考えものです。
また、不動産等は価値が減りにくいので2次相続でも課税の対象となります。
先のことも考えながら、ご家族にとって最も合理的な選択をしていきましょう。
根拠法令等
相法19の2